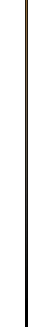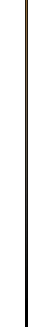スペシャル・インタビュー第2弾は、DOUBLEをはじめ、久保田利伸、平井堅、CHEMISTRY、EXILEなど、数多くのアーティストの作品を手掛けている音楽プロデューサー、松尾潔氏。氏が手掛けたサード・シングル「BED」の制作秘話や、当時巻き起こっていたR&Bブームについて、9年振りにタッグを組んだ最新シングル「残り火-eternal BED-」の話や、今後のジャパニーズR&Bの展望など、本当に多くの話を伺うことが出来たが、ジャパニーズR&Bを牽引してきた氏の発言は一言一言すべてに説得力があるし、興味深い話の数々に筆者もいちR&Bファンとして興奮を覚えながら話に聞き入ってしまった次第だ。この興奮をより多くの人と共有すべく、氏の話を出来る限り掲載した結果、かなりのヴォリュームとなってしまったが(実際のインタビュー時間、3時間半!)、他ではなかなか読むことの出来ない濃い内容に満足して頂けるのではないかと思う。
PART II :名曲「BED」の誕生、そしてR&Bブームではなくムーヴメントへ
――そしてサード・シングル「BED」をプロデュースされたわけですが、具体的にはどのような作業工程があったのでしょうか?
「「For Me」は数ある筒美京平さんの名曲の中でも、僕の中ではかなり位置付けが高い曲なんですね。にもかかわらず、DOUBLEの良さが出てないのはなぜなんだろうと思って。分析的に聴き込んでみると「For Me」の後奏っていわゆるアドリブとかフェイクと言われるものが全く入ってないんですよ。淡々と打ち込みが1分近く流れて終わるんです。こういうところに生きてる感じを入れなきゃいけないなと思って。音楽評論でよく言うところのスポンテイニアスなグルーヴを入れなきゃなと思ったんです。歌があまりに定規で測ったようなものをパチンパチンって当て込んでいるようにも聴こえがちだったから、そういう感じをなくしたいなと思って。そういうことが出来る人が必要だってことで、チームを2つ作りまして、その1つが当時僕が懇意にしていたマエストロ・Tさんとのチーム。ジャクソンズ「This Place Hotel」のベースラインを参考にしたトラックを彼と一緒に作ったんですが――それが「BED」になるんですが――そのトラックを何回も何回もループして、彼女達にマイクに向かわせて、とにかく感じたままフェイクしてくれって言ったんです。当時彼女達は1曲丸々作曲したことはないと言ってたんだけど、アドリブでヴォーカル・ラインが作れるってことは、作曲が出来るんだよと言って。なので彼女達にアドリブで歌わせて、そこから使えそうなフレーズを採譜して再構成しました。今となってみればどの部分が彼女達が歌ったものか覚えてないけど、サビの頭の部分はTAKAKOちゃんですね。もう一人別のプロデューサーと組んで曲と作って、いい方をシングルにしようと思ってたんですけど、圧倒的に「BED」の方が良かったんです」
―― アナログをきったり、リミックスでMummy-Dさん&KOHEIさんをフィーチャーしていましたが、日本のヒップホップ・シーンやクラブ・シーンのことも意識していたのですか?
「TAKAKOちゃんにいくら「体制側だ」と言われても(笑)、やっぱり僕には洋楽の発想があって。念頭にあったのはバッド・ボーイとソー・ソー・デフの売り方ですね。当時ソー・ソー・デフとバッド・ボーイがアナログでリミックスをガンガン出したり、お互いのアーティストをリミックスしあってたじゃないですか。ああいうのをすごく考えてましたね。あとこんなこと言うといい迷惑かもしれないけど、RHYMESTERの力を一方的に借りたつもりは全然なくて。一緒にスターになって欲しかったっていう、もっと上から目線で考えてました(笑)。RHYMESTERはその頃からその世界ではカリスマでしたけど、けど広い意味でのポップ・ミュージックとして正当な評価を受けていないこともわかってましたから。この人達がスターになってくれないと僕も楽しくないし、外国の音楽をただ紹介するだけの人生もイヤだなとどっかで思ってたと思うんです。僕の夢も詰まってたんですよ(笑)」
―― 「BED」がリリースされた頃はR&Bブーム真っ只中でしたが、今振り返ってみて、あのブームをどう捉えていますか?
「ブーム真っ只中の時から危惧はずっとありました。ブームと言われてるうちはどっかで終焉を迎えるわけじゃないですか。広告代理店に勤めている人達からはR&Bは今ブームって言われてるし、実際CMでもそういった人達のキャスティングする案も出ていると。けどこれ本当にヤバいよ。あと何年で終わるよ。R&Bから次のことを考えた方がいいよって僕に言ってくる人もいたんですよ。それは頭でわかっても、やっぱり好きだからR&Bから極端に離れるものは出来ないし。当時のインタビューでもこれはブームじゃなくてムーヴメントだってしつこいくらい言ってたんですけど、やっぱりブームって書かれたし。結局ブームは終わったということなんですよね。ブームって言うわかりやすい形になった時に、そこに乗っかればいいことがあるかもしれないって思う人が沢山出てくるんですよ。例えば、あそこに氷山が浮いてると。人気があって人もいっぱいいるから、とりあえずそこに行ってみようっていう人が増えてきて。なかには氷山を切り崩しながら南極の氷ですって売ったりする人も出てくるわけです。結果、氷山の形そのものを愛していた人(=DOUBLE)が一番割を食っちゃうんですよね。氷山を切り崩して売ってた人達は今タスマニアがカネになるらしいって聞いたらそっちに行っちゃうかもしれないけど、TAKAKOちゃんは9年前より小さくなったかもしれない氷山を今でも愛している人なんです。ツールとしてブームを見ていたか、R&Bをアティチュードやライフ・スタイルと捉えていたか、その違いだと思うんですけど。結局TAKAKOちゃんを含め、ライフ・スタイルまで提示できるほど器用な人が多くなかったから、ブームは終焉してしまったのかもません。あとR&B好きがそんなに増えなかったからっていうのも大きい理由だと思います。ブームの頃はR&Bが心底好きじゃないのに、やってる人も沢山いましたけど。その人達が真のR&Bラヴァーにはならなかったってことですよね。ナタデココと一緒です(笑)」
―― 便宜上“R&Bシーン”という言葉を使うこともありますが、結局のところ、R&Bシーンというものはあったのでしょうか?
「あったとは言えないと思うし、実際シーンを作るのは難しいなと思ってました。正直ブームでもムーヴメントでも呼び名はなんでもいいけど、シーンと呼び得るものを作らないとダメだと思っていたし、みんなで上にあがっていかないと本当に一過性の現象で終わってしまうと思ってましたね。でも売れてるアーティストを抱えているレコード会社の人からすると、なんで上の方にいる人間がこれからあがってくるヤツに手を貸してあげなきゃいけないんだっていう思いが大きかったみたいで。そんな中でシーンを作ろうなんて考える人は残念ながらいないですよね。アメリカのポップス業界における、物言わずとも肌の色だけでわかる連帯感は、残念ながら日本におけるR&Bにはなかったんです」
―― それでもシーンを牽引していかなくてはという思いはあったのですか?
「実際は牽引する立場にいるなってわかってましたよ。わかってたし、アメリカのR&Bシーンの成り立ちとか歴史とか、もっといえばやってる音の知識とかが僕より多い人はどこに行っても皆無なわけですから。僕がやらなきゃいけないんだろうけどとは思ってはいましたが、しかし当時の僕はあまりに若すぎました。自分のプレゼンテーションがうまくなかったっていうのも反省すべき点ですが、僕が言うことにたいして感情的な反発を持つ人があまりに多かったのも事実ですね」
―― けど松尾さんがジャパニーズR&Bを牽引していたと誰もが思ってると思いますよ。
「当時からよくそう言われましたけど、僕はラップをしませんから。当時アメリカは東にパフィ(P・ディディ)がいて、南にジャーメイン・デュプリがいて、西にはドクター・ドレイがいた。そういう人がプロデューサーとしてだけでなくアーティストとして前に出ることでシーンを牽引していたと思うけど、僕はそうではないですから。牽引するよりは後押ししていたい性質で。確かにジャパニーズR&Bという分野では最もサクセスフルなプロデューサーかもしれないけど、僕自身がリーダー・アルバムを出したいとは思ってませんから。実際出しませんかって話が来ても全部断ってますし。やっぱり違うんですよね。あくまで裏方としてシーンに貢献したいんですよ」
―― 先ほど松尾さんが「みんなであがっていかないとシーンは出来ない」と仰ってましたが、同じことを以前ZEEBRAさんやRHYMESTERの面々が言っていたんですね。だからこそ日本のヒップホップ・シーンは確立されたと思うのですが、R&Bに関してはそう思っていたアーティストが少なかったが故に、シーンが確立されなかったのでしょうか?
「ラップっていうのは、ラップすること自体がアティチュードの表明になり得るけど、歌い手は歌う場を奪われることに関しての恐怖感ってのが常にあるんですよ。TAKAKOちゃんみたいに、どんな所に行こうとも自分の好きなものを歌うって人もいるだろうけど、歌わせてくれるならなんでも歌いますって人達も沢山いるんですね。歌いたいっていう気持ちが強すぎて、何を歌いたいかってことが2番目3番目って人は大勢いるんです。そういう人達も必要だとは思うけど、R&Bを歌うことでスターになろうって思うことと、普遍的な人気を獲得できるだけの魅力があるっていうことは別のことなんです。DOUBLE以降の世代でその両方を高いレヴェルで出来てる人は、EXILEのATSUSHI君くらいだと思う。彼にしてもEXILEっていうところに入る必要があったわけだし、宇多田ヒカルちゃんにしてもあんなに歌が歌えるのに、彼女にとってはR&Bは“One of Them”なんですよ。贅沢な話ですけどね。けど世の中にそんなに才能のある人ってないし、いる必要もないと思ってるんです。限られた中でTAKAKOちゃんがいることが重要というか、10年間R&Bを歌ってるDOUBLEの作品群が残ってるだけで十分じゃないかとも思います。馴れ合い仲良しクラブとしてのシーンが出来るよりも良かったんじゃないかなとも思います。ま、半分は皮肉ですけどね(笑)」
―― そんな中で10年間R&Bから離れなかったDOUBLEは本当にすごいというか。強いアーティストですよね。
「そうですね。シビアに言えば大勝はしたことはないのかもしれないけど、とにかくいつも負けない試合を彼女は取り続けてきましたよね。引き分けかもしれないけど、負けないってことが10年続くと、大きな勝利に等しい価値を持つということなんでしょう。ビジネスという見地で考えると、企業に常に前年比っていう概念が付きまとうように、アーティストも前作比ってことを必ず指標にされるし、そこから自由でありたいと思っても、完全インディペンデントでやらない限りは無理ですよね。その中で彼女はずっと続けられるだけの結果も出してきてるわけですよ。商業的な結果を得た勝因は音楽性が高かったということになると思いますが、ただ勝つことだけを目的にしようと思ったら、(商業的な結果を得た)理由の一位が音楽性である必要はないんです。例えばイメージとか、時事性とか。ラップだってそうじゃないですか。ラップの上手さだけがすべてじゃないでしょ。僕ら世代だとそりゃあラキムが一番上手いさってなりますけど、けど言うことが面白いのはチャックDだし、諧謔性(かいぎゃくせい)っていう見地だったらビズ・マーキーが面白いし。歌も一緒だと思うんです。いつの時代にもスター歌手はいますけど、その人が今回はR&Bをやってみましたって説明しなきゃいけないところを、DOUBLEは説明する必要がないじゃないですか。DOUBLEっていう言葉の構成要素としてR&Bが初めからあるんです。音楽性の高さに加えて、そういう強みがあったからこそ、彼女は10年間ずっと変わらず自分の音楽を続けてこられたんだと思いますね」
次号へ続く (12.28更新)
第二回 音楽プロデューサー 松尾潔 PART1
第一回 トップ・ヘアメイクアーティスト 小野明美
もどる